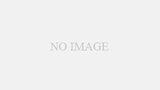マツヨイグサの主な花言葉は、下記のとおりです。
| 花の名前 | マツヨイグサ |
| 学名 | Oenothera stricta |
| 主な花言葉(日本) | 浴後の美人、気まぐれ |
| 主な花言葉(海外) | 無言の愛情、移り気 |
| 誕生花 | 6月21日、7月22日 |
| 開花期 | 5月~8月 |
花名は、宵になるのを待つように夕方に花を咲かせることに由来しています。
以下では、花言葉(日本と海外)の詳細を色別・国別にまとめ、その由来と名言などをご紹介します。
マツヨイグサの色別の花言葉
| 色 | 日本 | 海外(西洋など) |
|---|---|---|
| 黄 | 浴後の美人 | 無言の愛情 |
花言葉の由来(日本)
マツヨイグサは、江戸時代後期から明治時代初期に日本に伝わったとされています。
そんなマツヨイグサの花言葉は「浴後の美人」や「気まぐれ」。
夕方から明け方に黄色い中輪の花を咲かせ、花はしぼむと赤色に変色しますが、そんな花の生態から入浴後に頬を赤める女性を擬人化し「浴後の美人」という花言葉が付いたのでしょう。
また翌朝には花がしぼんでしまうところから「移り気」という花言葉が付いたとされています。
花言葉のある名言(日本)
恥じらいは、醜婦(しゅうふ)をも愛らしくする。
そして美人を一段と美しくする。
ーゴットホルト・エフライム・レッシング(ドイツの詩人・劇作家・批評家)
花言葉の由来(海外)
海外での花言葉は「mute devotion(無言の愛情)」と「inconstancy(移り気)」です。
これも日本の花言葉の由来と同様、マツヨイグサの花の生態に基づいています。
目立とうとせず、夕方にひっそり花を咲かせ明け方には花をしぼませるその様子から「無言の愛情」という花言葉が付いたのでしょう。
また1日しか花が持たず、しぼむと花の色を変えるところから「移り気」という花言葉が付いたとされています。
花言葉のある名言(海外)
真に愛する心の中では、嫉妬が愛情を殺すか、愛情が嫉妬を殺すか、いずれかである。
ーポール・ブールジェ(フランスの作家・詩人)
マツヨイグサの基本データ
| 花の名前 | マツヨイグサ |
| 学名 | Oenothera stricta |
| 和名 | 待宵草(マツヨイグサ) |
| 英名 | Evening primrose |
| 科 | アカバナ科 |
| 属 | マツヨイグサ属 |
| 原産地 | チリ、アルゼンチン |
| 開花期 | 5月~8月 |
| 草丈/樹高 | 10cm~30cm |
和名は「待宵草(マツヨイグサ)」といいます。宵になるのを待つように夕方に花を咲かせる花の生態にちなんでいます。
また学名の「Oenothera(オエノセラ)」は、ギリシャ語の「oinos(ブドウ酒)」と「ther(野獣)」を語源としています。根にブドウ酒のような香りがあるため野獣が好んだため、このような名前が付けられたとされています。
主な花の種類
| 種類名 | 特徴 |
|---|---|
| メマツヨイグサ | メマツヨイグサは荒地でもよく育つことから「アレチマツヨイグサ」とも呼ばれる。 直径3cm程度の小輪の花を咲かせる。 |
| アカバナユウゲショウ | 「ユウゲショウ」とも呼ばれる。 昼間に花を咲かせる品種。 |
| ヒルザキツキミソウ | 直径4cm~6cmの大輪の花を咲かせる。 良い香りを放つのが特徴。 |
保存方法
| タイプ | 一年草 |
| 花持ち期間 | 1日 |
| 出回り時期 | 3月~5月 |
| 耐寒温度 | 5℃ |
| 耐寒性 | 弱い |
| 耐暑性 | 強い |
| 日照 | 日当たりのいいところを好む |
| 耐雨性 | 普通 |
| 土質 | 水はけの良い土を好む |
| 利用方法 | 花壇、鉢植え |
おわりに
マツヨイグサの花言葉にまつわる由来や意味と、基本データについての紹介でした。
「ツキミソウ」とも呼ばれる「マツヨイグサ」は、栽培するのはそこまで難しくない品種ですが、丈夫な品種なので、お手入れをしないと庭一面がマツヨイグサになってしまうこともあるそうです。
しかし夜に黄色い可愛らしい花を咲かせてくれるため、注意しながら栽培してみるのも面白いかもしれませんね。